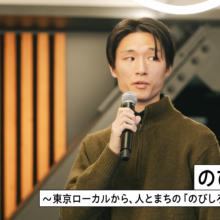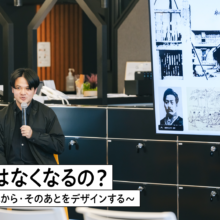2024年12月13日・14日に開催された「武蔵野美術大学実験区 DEMO DAY 2024」。14日のトークセッションでは、下北沢ボーナストラックの運営や地域活性化の実績を持つ小野裕之さんと、建築学科でまちづくりを研究する國廣純子さんをお招きしました。クリエイティブな発想を活かしながら、いかにビジネスとして持続可能な形を築いていけるのか。実践的な経験を持つおふたりの対話から、その可能性を探ります。
【ゲストプロフィール】
小野裕之
編集者・プロデューサー
1984年岡山県生まれ。中央大学総合政策学部卒。ベンチャー企業を経て2012年、ソーシャルデザインをテーマにしたウェブマガジン「greenz.jp」を運営するNPO法人グリーンズを共同創業。そのネットワークをいかし、16年に東京の伝統工芸の技術をいかしたジュエリーブランド「SIRI SIRI」、17年に秋田の米店や農家と組んだ「おむすびスタンド ANDON」、20年に発酵食品の専門店「発酵デパートメント」をそれぞれのパートナーとともに創業。20年春には、マスターリース運営会社として株式会社散歩社を創業し、現代版商店街「BONUS TRACK」を下北線路街にて開業。同施設でグッドデザイン賞ベスト100(21年)。その他、いくつかのブランドや店舗に出資、経営、アドバイザリー参画や事業売却を経験。目下、世田谷区にある旧池尻中学校(旧世田谷ものづくり学校)を創業支援型複合施設にリニューアルすべく奔走中。
國廣純子
武蔵野美術大学 教授、タウンマネージャー
慶應義塾大学経済学部卒業後、日本銀行調査統計局勤務。東京理科大学工二部建築学科を経て、三分一博志建築設計事務所にて犬島アートプロジェクトにて精錬所など一連の建築・ランドスケープのデザインを担当。2010年に拠点を北京へ移し、中国ローカルの都市計画・建築設計事務所にて国際プロジェクト責任者としてチームビルディングやプロジェクトマネジメントを経験。2013年より、自治体の市街地でのまちづくりを公民を問わず総合的に支援する仕事として、タウンマネージャーのキャリアをスタート。青梅市では10年間で130件の開業、あきる野市では6年間で50件の開業を創出。賃貸に出されていない空き店舗の調査や物件交渉から、開業を促進する情報発信やさまざまな事業企画を行い、面的な伴走支援によって特定エリアの価値と注目機運を高めるマネジメントを実践。
https://lit.link/localsustainableproject
【モデレータープロフィール】
酒井博基
武蔵野美術大学創業支援プログラムディレクター
武蔵野美術大学大学院修士課程修了。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科博士課程中退。ビジネスのシクミとシカケをデザインするクリエイティブカンパニー「d-land」代表。「六本木未来会議」「中央線高架下プロジェクト(コミュニティステーション東小金井)」「LUMINE CLASSROOM」などのプロデュースを手掛ける。
2016年グッドデザイン特別賞ベスト100及び特別賞[地域づくり]をはじめ、受賞歴多数。 書籍「ウェルビーイング的思考100 〜生きづらさを、自分流でととのえる〜」(オレンジページ)が2023年に出版。
ロマンを持続させるビジネスの本質
酒井博基(以下「酒井」):美大生の多くは、ビジネスを単にロマンを追求するための手段として捉える傾向があります。一方で、社会での実質的な機能やインパクトを考えると、経済的な視点も不可欠です。
ロマンを大切にしながらも、それをビジネスとして成立させるにはどうすればよいでしょうか。特に、ビジネスのロジックを取り入れ始めたときに、「ロマンがどこかに行ってしまった」と感じがちな現象について、どのようにお考えですか?
小野裕之さん(以下「小野さん」):ビジネスの本質は、単なる金もうけではありません。人生で最も多くの時間を費やす活動として捉えるべきです。持続的に時間を投資するためには、必然的に収益を生み出す仕組みが必要になります。最初に始めた人の想いが途切れても、お金が回っていれば事業を引き継ぐことができる。これは極めて重要なポイントだといえるでしょう。
世の中に継続しているあらゆるものは、なんらかの形でビジネス化されています。アートさえも、アートマーケットやパトロンという形でビジネスに支えられている。つまり、ロマンとビジネスは対立するものではなく、むしろロマンを持続させるためにビジネスの視点が必要なのです。

酒井:なるほど。ビジネスを人生の重要な一部として捉えることが大切なんですね。
國廣純子さん(以下「國廣さん」):私の経験からも、ロマンとビジネスの両立の重要性を感じています。
私は12年前に青梅市に移住し、地域の人々と伴走しながらプロジェクトを立ち上げ、10年で130件の開業を実現してきました。その過程で気づいたのは、事業計画がしっかりしている人ほど、将来的な不安要素を見つけてあきらめてしまう傾向があるということです。
たとえば、地元の有名ラーメン店主が街の起爆剤となるプロジェクトに興味を示しても、人口減少や周辺店舗の経営状況を過度に心配するあまり、最終的に踏み出せなかったケースがありました。一方で、「この街に住み続けたい」という強い想いを持つ人々は、さまざまな困難を乗り越えて事業を継続しています。ですから、大切なのは数字だけでなく、情熱と覚悟ではないかと感じたんです。つまり、ロマンを持ち続けることが、ビジネスを成功させる原動力にもつながるといえるでしょう。
創造性を育む対話の旅
酒井:今回の実験区では、おふたりにメンターとしてご参加いただきました。メンタリングを通じて感じたことをお聞かせください。
國廣さん:メンタリングをしていると、思わぬ方向に話が広がったり、最初に言っていたことが急になくなったりすることがあって、私のメンタリングに問題があるんじゃないかと毎回反省していました。でも、小野さんのほうでも同じようなことが起きていたと聞いて、少し安心しました。
私が担当したプロジェクトでは行政と組む必要があったので、行政や地域のステークホルダーと一緒にプロジェクトを立ち上げる際の重要なポイントを伝えることを心がけました。でも、あまりにも細かくルートを敷きすぎると、学生たちのチャレンジ精神や創造性が損なわれる恐れもあり、そのバランスを取るのが難しいなと感じましたね。
小野さん:たしかにバランスを取るのは難しいですね。
私のアプローチとしては、ビジネスを単なる金もうけではなく、より広い視点で捉えることに重点を置きました。事業の継続性はお金の循環に依存しており、これは個人の収入を増やすという動機を超えた問題です。
こうした背景から、メンタリングでは、“ロマン”寄りの議論とビジネス=“ソロバン”寄りの議論を交互に行うようにしました。このふたつの側面を「反復横跳び」のように行き来することで、よりよい結果が得られると考えたからです。 あわせて、思考と実践のバランスも重要です。頭の中で考えているだけでは、本当にやりたいことかどうかわかりません。サッカーの観戦とプレーの違いのように、ビジネスも実際に体験してみないと、本当に自分に合っているかどうかわかりませんよね。

完璧を超える、クリエイティブな挑戦
酒井:美大生特有の特徴について、私は完成度を重視する傾向が強いように感じたのですが、おふたりはどのような印象を持ちましたか?
國廣さん:美大生、特に教授を務めているムサビの建築学科の学生は非常に真面目で、完璧を求める傾向があります。しかし、これが納得いく出来になるまで悩んでしまい提出ができなくなってしまったり、途中経過でも割り切って評価を受けることへの抵抗にもつながっているかもしれないと思い、私の担当する設計スタジオでは「テストマーケティング」という概念を導入しました。
具体的には、3週間にわたる継続的なレビューを実施したんです。通常、建築学科では最終日に提出された上位作品のみを常勤教員やゲストの建築家を招いて講評会で評価しますが、私たちは学内レビューに加えて社会でまちづくりに関わる異分野からのゲストを多く招き、頻繁なフィードバックの機会を設けました。こうすることで、多くの学生が建築分野でのデザインに絞られた価値観だけに頼ることなく多様に改善されていく様子が見られたんです。「テストです」という形で意見を聞くことで、学生たちの抵抗感が減り、むしろ積極的な取り組みにつながりました。
酒井:テストマーケティングの導入は画期的ですね。小野さんはどうお考えですか?
小野さん:美大の教育では、クライアントワークのように、リスクを他者が負う前提が多いように感じます。特にコンペ形式では、テスト的な市場投入なしに初お披露目という形でアイデアを発表することが強調されがちです。しかし、スモールビジネスや作家として生きていく場合、自分でリスクを取って市場に問いかけていく必要があります。
そのためには、投資家や金融機関といった、コンペでは出てこないステークホルダーとの関係構築も大切です。マーケットは消費者が相手だけのものでなく、これらの出資者に対するものも存在します。説明して当ててみて、足りない部分や弱いロジックを見つけ、ブラッシュアップしていくことが重要です。
同じ金融機関でも担当者によって判断が異なるケースもあるので、実際に対話を重ねることでリアルな意見を聞くことができます。教育機関の中でも、こういった実践的なアプローチをクライアントワーク、コンペ形式でないもうひとつの仕事のつくり方として、起業家や、あるいは金融機関の担当者を授業に招いて、それぞれの視点を受け取るなど、きちんと組み込んでいく必要があるのではないでしょうか。
酒井:実践的なアプローチの重要性がよくわかりました。教育機関でもそういった機会を設けることが大切なんですね。

小さな一歩から大きな成果へ
酒井:事業を始める際の具体的なアプローチについて、お考えをお聞かせください。特に、資金面での障壁を感じている学生も多いと思うのですが。
小野さん:この社会では、実際にはそれほど大きなリスクは取れないようになっています。なぜならば、やったことがない人には与信がないからです。借入れを考えた場合でも、最初は日本政策金融公庫から100〜200万円程度を借りて、それを10年くらいかけて返済していく。つまり月々1万円程度の返済から始まるわけです。
世の中には多様なマーケットがあり、出店やクラウドファンディング、キッチンカーなどを活用して、まずは一度売ってみることが大切です。たとえば、メルカリは日本一巨大なセカンドハンドのマーケットですから、出品者が自分で集客する必要がありません。スマートフォンで写真を撮って出品するだけで、自分がおもしろいと思うものが売れるかどうかを試すことができます。
酒井:小さなリスクから始められるというのは、学生にとって心強い情報ですね。國廣さんはいかがでしょうか?
國廣さん:行政や地域の方々との関係構築は、まさにそうした小さな一歩から始まります。実験区で私がメンターを務めた方の例では、北海道月形町に通い続けることで信頼関係を築き、最終的には地元の方々とまちづくり会社を立ち上げるまでに発展しました。これは継続的な行動から生まれた成果であり、机上の構想だけでは到達できないものでしたね。
酒井:行動することは非常に重要ですね。
小野さん:行動力は共感を生み出し、その共感が金銭的な支援にもつながります。アイデアのすばらしさよりも、具体的に動いた人に共感とお金が集まる傾向があります。これは実際の現場でよく目にする光景です。
今日のプレゼンテーションを聞いていても、行動した人と、まだ行動していない人では、その差が大きいと感じました。もちろんアイデアも大切ですが、それだけが最重要ということではなく、また動けば動くほどリスクは下がり、自分だけでなく他の人も一緒にリスクを取ってくれるような環境が生まれます。
國廣さん:私の経験でも、根拠のない自信のようなものを持って突き進むことが大切だと感じています。
タウンマネージャーの仕事は大抵の場合、まったく知り合いのいない街に入って、「この街をV字回復させてください」みたいな要望から始まることが多いです。KPIやそれを達成するための事業から考えなくてはならない。知り合いもいないし、雇われているだけの立場で、使わせてもらえる予算もない状況でした。街をV字回復させる確信なんて当初はもちろんゼロだったんですけど、リサーチを進め仮説を立て実証することを繰り返しながら、「私はできるはずだ」くらいの根拠のない自信みたいなもので突き進むことで、周りの人がついてきてくれたんです。そういう経験から、なにごとも最初からあきらめるのではなく、的確にリサーチを進めながら自信を持って行動することの重要性を実感しています。

ロマンとリアルが交差する場所で
酒井:最後に、美大生には今後どのような可能性があると思いますか?
小野さん:私はこれを「ロマンとソロバン」の問題というより、「ロマンとリアル」の問題だと考えています。考えているだけでは、本当にやりたいことかどうかわかりません。たとえれば、初恋の人に永遠に恋をしているようなもので、実際に付き合ってみないと、本当の相性はわからないですよね(笑)。
芸術家やデザイナーの方々も、生計を立てるうえでさまざまな工夫をされています。時には右腕となる人材に経営面を任せることもあるでしょう。それは決して妥協ではなく、自分の得意分野に集中するための現実的な選択だと考えています。
日本ではまだまだ、若いころからお金に向き合うことはなにか、やりたいことの純度を下げてしまうような発想が根強いと感じることがありますが、たとえば、地方で仕事をしていると、お味噌屋さんのような商店では、従業員もお父さんお母さんも、会社の財布も家計の財布も、すべてが一体となっています。子どものころからそういった現実を目の当たりにしていても、決して間違った大人に育つわけではありません。むしろ、こういった生々しい部分も含めて、多様な経験や価値観を認め合える環境をつくっていく視点が、仕事のあり方が多様になっていくいま、より大切なのではないでしょうか。

酒井:リアルな経験の重要性がよくわかりました。國廣さんはいかがでしょうか?
國廣さん:建築の世界でも、すべての仕事を作家性の高いものにする必要はありません。ある建築事務所では、作家性の高い仕事はAランク、お金は稼げるけれど人には見せたくない仕事はCランクというように、世間に公表するランクを区分して自分なりのマネジメントをされています。
ただ、こういった現実的なマネジメントの知識は、学生時代になかなか学ぶ機会がないんですよね。本学の建築学科にも、いま非常に人気のあるアート専門の先生がいらっしゃいますが、その方も「実は装飾の仕事なども手がけていて、必ずしもすべてが作家性の強い仕事ばかりではない」と話されていました。そういったバランスの取り方を、学生のうちからもっと知る機会があればいいなと考えています。