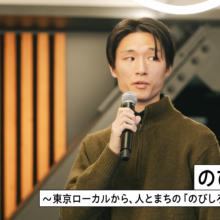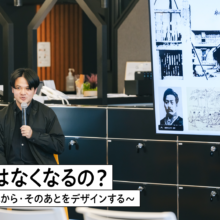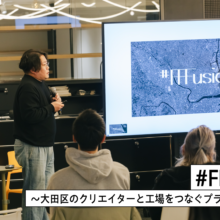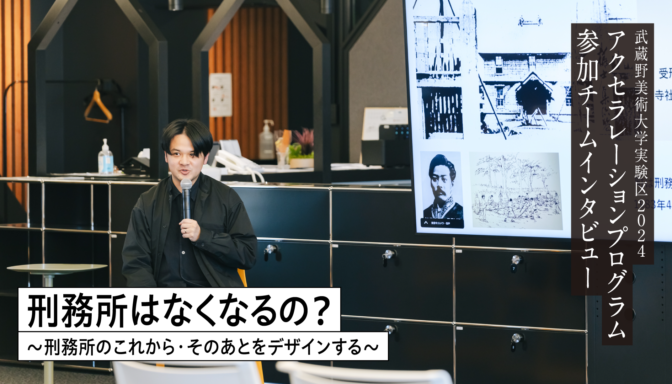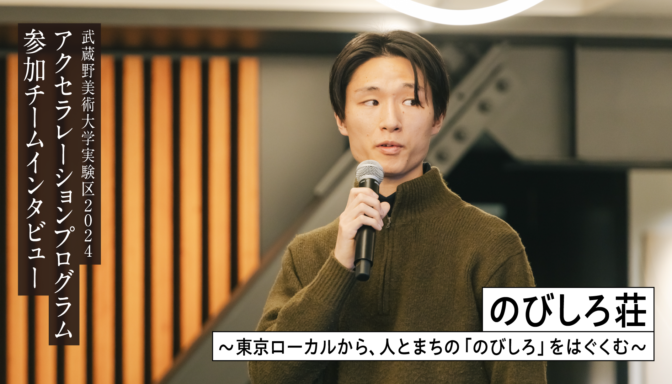2024年12月13日・14日に開催された「武蔵野美術大学実験区 DEMO DAY 2024」。初日となる13日のトークセッションでは、住友商事株式会社 ライフスタイルグループ 未来デザインチーム マネージャーの市村和哉さん、株式会社HEART CATCHの代表取締役であり武蔵野美術大学 客員教授の西村真里子さんをお招きし、「クリエイティブ人材はチームの中でどのような価値を発揮するか」をテーマに、さまざまなお話をうかがいました。
【ゲストプロフィール】
市村和哉
住友商事株式会社 ライフスタイルグループ 未来デザインチーム マネージャー
慶應義塾大学理工学部1995年卒、住友商事入社。ライフスタイルグループにて、雑誌連動EC、インターナショナル幼稚園・学童、ネットスーパー等の新規事業の立ち上げに従事。2023年度に、グループ内に未来洞察ラボ「DEZART LAB」を立ち上げ、運営中。国家資格キャリアコンサルタント。ライフシフト・パートナー。サウナ・スパ健康アドバイザー。
西村真里子
株式会社HEART CATCH 代表取締役/プロデューサー、武蔵野美術大学 客員教授
日本IBM ITエンジニアとしてキャリアをスタート。グローバル言語検索タクソノミーで特許取得。後、アドビシステムズのフィールドマーケティングマネージャーに従事。2011年、クリエイティブ企業バスキュールにプロデューサーとして参画。カンヌライオンズ金賞受賞。2014年株式会社HEART CATCH共同創業。2020年米国ロサンゼルスにHEART CATCH LA共同創業。テクノロジー&クリエイティブのキャリアを活かし、企業や自治体の新規事業案件の企画に多く携わる。日米のスタートアップに投資しグロース支援、オペレーション支援を実施(J-Startupサポーター)。
内閣府日本オープンイノベーション大賞専門委員会委員、Art Thinking Collective(仏パリ / ビジネススクール ESCP)インストラクター。Forbes Japanオフィシャルコラムニスト。武蔵野美術大学 客員教授。静岡県フェロー。
【モデレータープロフィール】
酒井博基
武蔵野美術大学創業支援プログラムディレクター
武蔵野美術大学大学院修士課程修了。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科博士課程中退。ビジネスのシクミとシカケをデザインするクリエイティブカンパニー「d-land」代表。「六本木未来会議」「中央線高架下プロジェクト(コミュニティステーション東小金井)」「LUMINE CLASSROOM」などのプロデュースを手掛ける。
2016年グッドデザイン特別賞ベスト100及び特別賞[地域づくり]をはじめ、受賞歴多数。 書籍「ウェルビーイング的思考100 〜生きづらさを、自分流でととのえる〜」(オレンジページ)が2023年に出版。
組織における「枠外思考」の重要性
酒井博基(以下「酒井」):さっそくですが、本日のトークイベントのテーマ「クリエイティブ人材はチームの中で どのような価値を発揮するか」に対する第一印象を教えてください。
市村和哉さん(以下、市村さん):「クリエイティブ人材」の意味を取り違えないようにしないといけないなと、先ほど西村さんと話していたところです。 私は昨年「カンヌライオンズ」(フランス・カンヌ市で開催される世界最大級の広告賞)に参加したのですが、社内でその報告をした際に「クリエイティブ」という言葉を使ったら「なにをかっこつけてるんだ」と言われたんです。でも、商社で働いている人って、本来はみんなクリエイティブなはずですよね。新しい事業をつくったり、海外でなにかつくろうとしたりするのはクリエイティブな行為なのに、多くの人はそう捉えていない。同様に「デザイン」という言葉も表層的な意匠造形のことだと思われがちです。でも、「設計(design)」というと理解してもらえるんですね。こういったカタカナ言葉が誤解される怖さがあるなと思います。

西村真里子さん(以下、西村さん):酒井さんは、美大出身のいわゆる「クリエイティブ人材」として、世の中の人と話すときに戸惑いを感じることはありますか?
酒井:「クリエイティブ人材」という言葉に対して誤解を抱いている人は、その輪郭をつかもうとする意思があるので、むしろお互いへの理解を深めていくことができると思うんです。
しかし実際には、“クリエイティブな人”とはどういう人か?とイメージすらしたことがない人の方が多い。自治体から「クリエイティブな人たちを地元に呼び込みたい」と相談されたりするなかでは特にそう感じますね。「クリエイティブなんてまったくわからないです」という人は、本当にわからないのか、それとも自ら壁をつくっているのかどちらなのかなと思います。 一方で、僕は美大でマーケティングを教えているのですが、授業の初日は学生たちの強烈な壁を感じます。

西村さん:クリエイターやアーティストは「マーケティング」や「広告代理店」という言葉に拒絶反応を示す方が多いですね。もしかすると、自分の力だけでものづくりをきわめたいという職人気質が強いのかもしれません。でも、分業が進んだり、AIが出てきたりと、人間そのものがよりクリエイティブにならなければいけない現在、横とのつながりや協業が必要になっていると思います。
酒井:住友商事さんではクリエイティブ人材を総合職として採用されていますが、どう見ていますか?
市村さん:元デザイナーなどのクリエイティブ人材を積極的に中途採用しているのですが、採用したのはいいけど、受け入れ先の上長がその人をどう扱えばいいのかわからないという状況が見られます。また、3〜4年で部署異動があるので、採用した上長がいなくなり、次の上長がくると「必要ない」と感じられてしまうこともあります。まだまだ難しさを感じますね。
西村さん:私の場合は、「異ジャンル」や「よそ者」の枠として新しいプロジェクトに入れられることが多いんです。あるとき、自治体の経営者団体に呼ばれ、300名くらいの前で講演をしてほしいとご依頼をいただいたことがありました。「いつもの格好でいいよ」と言われたので革ジャンに緑色の髪で行くと、ほかの方は全員スーツ。空気が凍りつくのを感じました(笑)。そういうとき私は、受け入れてくれないマジョリティに迎合するよりも、信頼して声をかけてくださった方のことを考えて、あえて「異物」のままでいるようにしているんです。
いまでも、そのような畏まったビジネスの場に新規事業やプロジェクトの話をしてもらいたいと呼ばれたらあえて「異物」を装う服装で行くこともあります。最初は少し驚かれても、真面目に仕事をしていると徐々に「スーツだけを着ているのがビジネススタイルではない」と、見た目や慣習だけにとらわれずに話を聞きいれて下さるようになってくる。そうすると、新しい提案も受け入れられやすくなるんです。クリエイティブ人材をチームのなかに入れるときは、異物感を演じつつ、やるべきことをやり続けることが大切だと、ここ数年感じています。
市村さん:たしかに異物は異物であり続けた方がいいと思います。同じことでも、異物感のある人が言うと「あの人が言うのならそうなのかな」と思われたりする。西村さんを呼んだ方も、もしかしたら「自分が言っても通じないことを代弁してもらいたい」という意図があったのかもしれないですね。
また、「異物」と同じような意味で「枠外思考」も重要だと思います。たとえば、同じメンバーだと堂々巡りになりがちな会議でも、いつものメンバーではない「枠外」の人の言ったことがすごく響くことがありますよね。昔は枠内だけで続けていてもなんとかなりましたが、これからは不確実で複雑なVUCAの時代です。それに気づいている組織は、枠外から人材を採用しています。でもうちの会社のように、採ったはいいけど使い方がわからない、お互いにいい状態をまだつくれていないという課題を持っている組織も多くあると思います。
酒井:市村さんは、住友商事でその状況を変えていこうとされていますが、しんどさは感じますか? 市村さん:それはありますね。どんな組織でも、100人いれば20人は賛成しても20人は反対しますし、それ以外の60人は無党派層です。僕ひとりが言っていてもダメなので、ムサビの先生や、他社のクリエイティブ人材を招いて話をしてもらっています。そうすることで、徐々に賛成派が増えてきていると感じます。

起業家に必要なメンタリティが培われる、美大の「講評会」
酒井:起業するうえでの美大生の強みについてどう考えますか? たとえば「講評会」は美大特有の文化ですが、そこで起業家に必要なレジリエンス(回復力)が鍛えられるところはあるかと思います。
西村さん:おっしゃる通り、一般の大学では人前で発表する機会はあっても、作品を並べてみんなの前で講評されるという経験はないですよね。あるとき、美大生と一般の方が一緒にいる場で講評会のようなことをしたら、一般の方が「なんでそんなことを言うんですか」と怒り出したことがありました。でも褒めるだけでは、それ以上のフィードバックができないし成長の機会もありません。大学時代に講評会で悔しい思いをした人は、社会に出てから自分がつくったものを発表することに対するハードルが下がるのではないでしょうか。
市村さん:僕も講評会という経験は美大生の強みだと思います。また、講評では先生によって評価がまったく違ったり、正解を教えてくれなかったりすることもある。正解を求めることに慣れている僕のような人たちにとってはすごく新鮮です。そういう意味でも、講評会のようなことはこれからの時代にすごく求められると思います。小学校から高校まで、全部の教育で取り入れたほうがいいですよ。
プロトタイピングに見るクリエイティブ人材の可能性
酒井:美大生はレジリエンスは強いのですが、みんなが経済活動に興味があるわけではないというのがおもしろいところです。実験区の創業支援プログラムはクラフトマンシップにアントレプレナーシップを掛け合わせて、美大の“ネクスト”をつくっていくための出会いの場。そこでやはり大切なのがチーム組成だと思うのですが、どういう形が望ましいのでしょうか。
市村さん:クリエイターといっても、絵を描くのは上手だけど、クライアントのオーダーにかなうものを全然つくれないというケースはよくあるので、クリエイター同士であればなんでもいいということではないですよね。ちゃんとわかっている人が組み合わされればいいのですが。 西村さん:これは実験区に対する要望なのですが、私がなにかのプロジェクトを立ち上げて「ここに現役の美大生がいたら絶対におもしろくなるのに」と思ったときに、どこに頼んだらいいのかわからず困ることがあるんです。そういった外部からの「美大生と組みたい」という要望には応えていただけるのでしょうか。

酒井:もちろんウェルカムです。ただ、美大生を呼びたい理由として最も多いのが「ちゃちゃっと絵を描けるんでしょ」だったりするんですよね。そういった要望には応えづらいということを、どのようにして誤解なく発信すればいいのか悩んでいます。
市村さん:社内のアート思考のワークショップに美大生がファシリテーターとして入ってくれると、ビジネスパーソンたちの目が開きます。それまではパワポでプレゼンするのが正解だと思っていたけれど、造形や歌などいろいろな様式を使うことで、より伝わりやすくなるということに気づくんですよね。いまはプロトタイピングがいろいろなところで求められているので、最初からプロジェクトメンバーとしてクリエイティブ人材を入れることが大切だと思います。
酒井:たしかに、プロトタイピングというフェーズではすごく活躍できるだろうなと思います。言語化からこぼれ落ちているものをいかに具体化するかというディスカッションに役立ちそうですね。
市村さん:実際に、僕が審査員を務めた実験区の最終選考でも、非常食をきれいなお弁当にして持ってきたチームがグランプリを獲得しました。ほかのチームはそういうプロトタイプ的な見せ方をしませんでしたが、人間はリアルなものを持ってこられると共感するんです。そのことが徐々に理解されつつあると感じています。
酒井:実験区が“プロトタイプラボ”になっていくといいかもしれないですね。
西村さん:そうなると、企業や自治体がやろうとしていることのさまざまなエッセンスが実験区に集まってくるようになりますね。もしかしたら「依頼主が平面的なものを依頼しようとしたら、空間的なものが返ってきた」みたいに、ビジュアルづくりにとどまらない美大の可能性を提供できるかもしれません。酒井さんがおっしゃっていた、美大生に対する誤解を覆していくような場にもなっていくのではないでしょうか。

美大生の最適なマッチングを図る「実験区」のこれから
市村さん:僕自身の体験でもあるのですが、どのビジネスアイデアにどのクリエイティブ人材をマッチさせるか、そのマッチングを誰がするのかはすごく難しい問いだと思います。クリエイターによって得意なことが違うし、事業フェーズによっても異なりますよね。
西村さん:たとえば、実験区に参加してポートフォリオを出してもらい、好みやスキルがわかるようにしておくのはいかがですか。
酒井:それは可能だと思います。ただ、美大生って忙しいんですよね。授業も課題づくりもあるし、アルバイトをして制作費を稼がなければいけない。
西村さん:そのためにも、企業からいい金額でプロトタイプの発注を受けられたらいいですよね。
酒井:プロトタイピングの仕事が、作品の制作費を稼ぐアルバイトになっているという構図はおもしろいです。それから、学生同士のコラボレーションについてはいかがでしょうか。
西村さん:実験区の参加者から、美大生と組めることは大きなメリットだという話を多く聞いたので、インカレみたいなことは積極的にやってもらいたいと思います。私のスタートアップ研究の授業でも、アプリをつくれる人やエンジニアと組みたいけど、なかなか接点がないという声を聞きます。美大生と理工系のプログラミングを学んでいる学生など、あえて遠い分野同士のマッチングができると、そこから新しいアイデアが生まれそうですね。
市村さん:東大や慶應大の出身者だけで構成されたスタートアップをよく見ますが、そこに美大出身者という「異物」が加わりつつある。また、企業も商品やサービスを他社と共創するようになってきています。これはいい傾向ですよね。
西村さん:いまのお話を聞いて思い出したのですが、私は東大卒の子たちが立ち上げたスタートアップに、多摩美の方を紹介したことがあるんです。すごく喜んでもらえて、その方はそこで働くことになりました。いまはいろいろな企業や学校のなかに起業部があるので、そういったところと美大生をマッチングすると、スタートアップのビジネスとしていい跳ね方をすると思います。 酒井:おふたりの話を聞くと、美大生への誤解を解こうとするよりも、プロトタイピングのような一緒に手を動かすことを通して体感してもらうことで、実験区の可能性を広げることができるのではないかと感じました。「実験区にくるといいチームが仕上がる」と期待を持ってもらえるように、この取り組みを育てていきたいと思います。