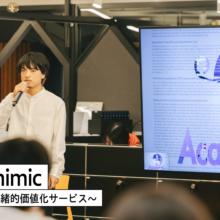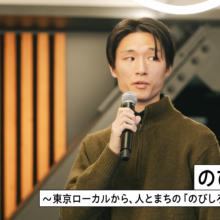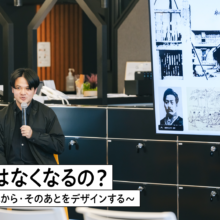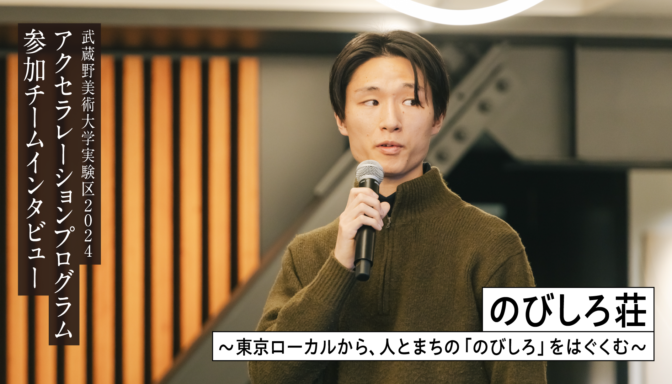2024年度の武蔵野美術大学実験区「MAU SOCIAL IMPACT AWARD」で入賞し、アクセラレーションプログラムに進んだチームにインタビュー。今回は、クリエイターと町工場の新しい関係性を模索する「#FFFusion ~大田区のクリエイターと工場をつなぐプラットフォーム~」のチームにお話を聞きました。メンバーのうち、家業である製造業のかたわら事業開発を手がける代表者の瀧原慧さんと、武蔵野美術大学 クリエイティブイノベーション学科4年の安里太樹さんに、プロジェクトの展望について伺います。
▼チームメンバー
代表者:瀧原慧(Counterpoint 代表、城南工業株式会社)
安里太樹(武蔵野美術大学 クリエイティブイノベーション学科4年)
河俊光(プロダクトデザイナー)
▼マネージャー
永井史威(Hi inc 代表、ディレクター・エディター)
▼メンター
石井挙之(武蔵野美術大学 客員准教授、株式会社仕立屋と職人 代表取締役)
プロジェクトの原点とメンバーの多様性
―まずはプロジェクトの概要について教えてください。
瀧原慧さん(以下「瀧原さん」):「#FFFusion」はチーム名でありプロジェクト名でもあります。掲げているビジョンは“このまち、大田区をクリエーションのパートナーに”。大田区の地域産業である金属加工を主とした製造業と、作家活動を行うアーティストやプロダクトデザイナー、それからハードウェアベンチャーなどのクリエイターを、工場見学ツアーの実施や受発注の伴走を通してつなぐプロジェクトです。
―どのようなきっかけで始まったのでしょうか?
瀧原さん:僕の家は、母方の祖父の代から大田区で約60年続く鈑金加工会社を営んでいます。そんな背景から、クリエイターやデザイナー、アーティストの方々が金属加工でやりたいことを実現するためのサポート役としていろいろな活動をしてきました。 2020年には、京急電鉄が主催する、大田区の工場とクリエイターを組み合わせたプロジェクトで両者の間に立つコーディネーターのような役割を担当。ほかにもデザインリサーチャーとしてプロジェクトの立ち上げや戦略策定にも関わるなかで、渋谷にある共創施設「SHIBUYA QWS」でチームメンバーの安里くんと出会ったんです。

安里太樹さん(以下「安里さん」):僕はSHIBUYA QWSでスタッフとして働いていて、瀧原さんはそこの利用者でした。ムサビでものづくりを学ぶなかで金属加工に興味を持ち、そのことを瀧原さんに相談したのが始まりでしたね。それからほどなくして実験区の募集を見つけ、チームを組んで参加しようということになりました。
―現在のチームの体制について教えてください。
瀧原さん:僕たちのチームの特徴は、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まっていることです。僕と安里くんのほかにもうひとり、もともと電気機器メーカーで働いていたプロダクトデザイナーの河俊光さんというメンバーもいて。河さんとは大田区の工場とデザイナーをつなぐプロジェクトで出会い、それから一緒に製品開発の仕事をしていて、今回のプロジェクトでも、製造業とデザインの両方の視点を持つメンバーとして貴重な意見をもらっています。もうひとり、グラフィックを担当するメーカー勤務のデザイナーもいます。
4人がそれぞれに持つ製造業の視点、デザインの視点、そして学生ならではの新鮮な視点が有機的に組み合わさることで、新しいアイデアが生まれています。
安里さん:僕の役割は時期によって変化してきました。実験区に参加した当初は主に資料作成を担当していて、瀧原さんのアイデアを整理したり、コンセプトをブラッシュアップしたりする役割でした。その後は、Webデザインやクリエイティブの部分を担当しています。
瀧原さん:安里君は本当にオールラウンダーで、なんでもできるところが心強いですね。それに、プロジェクトに対する熱意もすばらしい。報酬などは出ないのですが、みんなのやりたいことが一致して、各々が主体的に動いてます。
ものづくりの新しい可能性を広げていきたい
―実験区について、どのような印象を持っていますか。
安里さん:率直に、めちゃくちゃいい取り組みだと思っています。選考の時点で、学生から熱量のあるプランの数々を聞けたのがうれしかったですね。それから、なんといってもマネージャーである永井さんとの出会いが大きかったです。
瀧原さん:そうだよね。みんな永井さん大好きで(笑)。
安里さん:いろんな事例を出しながら話してくださって、僕たちの熱意や想いを丁寧に整理してくださいました。活動の方向性を決めるうえで、大きな影響を与えてくれましたね。最初は金属加工をわかりやすく伝えようとか、工場とクリエイターの仲介に入ろうというふわっとしたものだったのが、具体的にどうなっていきたいのかまで整理できたのは、永井さんのおかげだと思います。
瀧原さん:一般的なビジネスコンテストでは、指導者としてアドバイザーの方がつくことは多いと思いますが、実験区のように伴走したり、下から支えてくれるマネージャーがついてくれるのは画期的なのではないでしょうか。
安里さん:僕は山登りが好きなのですが、エベレストなどではシェルパと呼ばれる現地の案内人がいて。登頂するためのいろいろな手助けをしながら一緒に登ってくれるのですが、実験区のマネージャーもそのシェルパのような心強い存在だなと感じていました。
また、アイデアを形にしたり、プロジェクトを進めるうえでは、やっぱり“締め切り”の存在は大きいと感じました。その点も実験区に参加してよかったことのひとつです。締切直前に完成度が爆発的に上がるような現象って、美大生あるあるですよね。でも、それは単なる追い込みではなく、アイデアを練り上げてきた結果としての集中だと思います。
瀧原さん:そうそう。最終プレゼンに向けて試験的にプレ工場ツアーを行ったのですが、それも実は1週間くらい前まで日取りさえ確定していない状態でした。そこから短期間で実施まで持っていったときは、みんなの底力を感じましたね。
コンセプトもかなりの時間をかけてコンセプトを練り直し、最終的な形に至るまでには紆余曲折がありました。その過程で自分たちのやりたいことが明確になっていった気がします。

―今後はどのような展開を考えていますか?
瀧原さん:まず、見学に行った工場の方々と一緒に製品開発をしようという話が進んでいます。単なる受発注の関係ではなく、一緒にものづくりを考えていける関係性を築いていきたい。あとは、情報発信の面でも力を入れていきたいと考えています。
安里さん:WEBサイトの制作も進めていて、現在ワイヤーフレームまで作成済みです。しっかりとしたブランディングをすることで、クリエイションと製造業の両方をきちんと理解しているという強みを示していきたいですね。
瀧原さん:そうですね。2025年3月ごろに法人化することも視野に入れています。最近では、製造業の知見やクリエイターとの協業に関するノウハウを、サブスクリプション形式で提供するアイデアも出てきています。収益化も見据えながら、持続可能な形でプロジェクトを展開していきたいと考えています。
―ありがとうございます。最後にひと言ずつ、今後の抱負をお願いします。
安里さん:美大生としての感性と、製造業の現場をうまくつなげていけるように、これからも挑戦を続けていきたいです。いま進めている卒業制作でも金属加工を活用していて、その経験も#FFFusionに活かしていけたらと思います。
瀧原さん:大田区からものづくりの新しい可能性を広げていきたいですね。工場とクリエイターが出会うことで、どんな化学反応が起きるのか。その場づくりを通じて、日本のものづくりの未来に貢献できればと思います。